いつの時代も世間は母親に厳しい視線を向ける。
不本意なレッテルを貼られないように、防衛せざるを得なかった母親たちを、私は責めきれないと思う。
けれどその防衛が、“愛情の過剰投与”になってしまうことがあるのも現実。
「薬も用法を間違えると毒になる」。
ふと、そう思ったとき、私は“毒親”という言葉の意味を、少し違う角度から見たくなった。
もしかしたら、“毒親”と呼ばれる人たちは、
愛情という薬の使い方を少し間違えてしまっただけなのかもしれない。
愛情は本来、“薬”のようなもの
愛情は、子どもを安心させ、心を育てる“栄養”であり“予防薬”であり“治癒薬”。
それが適切な量なら、子どもにとってかけがえのない支えになる。
でも、もしその薬を「早く効かせよう」と思って多めに与えたら?
あるいは「この薬なら安心」と思い込んで、効き目を確かめずに続けたら?
どんな薬でも、過剰投与すれば副作用が出る。
愛情も、それと同じではないか?
「あなたのため」という名の過剰投与
“毒親”と呼ばれる人たちは、
きっと最初から子どもを苦しめたいと思っていたわけではない。
「不安や心配」
「子どものためを思って」
「間違わないように」
その気持ちは本来、予防であり、手当てであり、保護のはずだった。
でも、正しい目的が、誤った方法で投与されてしまうと、
それは“愛情”ではなく“支配”に変わってしまう。
けど、子育て中はそのことに、気づけない…。
親の性格と子どもの体質がつくる“相互作用”
薬にも、体質や相性があるように、
親の性格と子どもの気質の“組み合わせ”が、関係性を大きく左右する。
同じ言葉でも、ある子には響き、別の子には傷になる。
同じしつけでも、兄には効いて、妹には副作用が出る。
つまり、“毒親”というのは絶対的な存在ではなく、相互作用の結果。
親の「性格」と子どもの「感受性」
そこに“愛情の用量”が重なって、初めて「薬」か「毒」かが決まるのだと思う。
“毒親”とは、愛情の処方を誤っただけかもしれない
薬を正しく使うには、知識と観察が必要。
しかし親もまた、人を育てながら自分を知る“学びの途中”にいる。
だから、「毒親」と決めつけるよりも、
「どうして副作用が起きたのか?」を見つめ直す方がずっと建設的だ。
もしかしたら、それは“悪意”ではなく、愛情の処方ミスだったのかもしれない。
親も人間、子もまた体質を持っている
親も子も、どちらか一方だけが悪いわけじゃない。
ただ、それぞれに“心の体質”がある。
愛情という薬は、万能ではない。
でも、処方を見直せば、また効き始める。
“毒親”という言葉の下に隠れているのは、
もしかすると、不器用な愛情と理解のすれ違いだけなのかもしれない。
🌿後書き
人がこの世に生まれて、最初に与えられる環境が「親」だ。
それは“最初の居場所”であり、同時に“選べない環境”でもある。
そして、その場所が必ずしも安全で、自分にとって最善の環境とは限らない。
日本に生まれた私たちは、当たり前すぎて気づかないことが多いけれど、
この世界には、そもそも“安全な場所”などどこにもない国もある。
だからこそ、どんな環境にも“何かを教えてくれた意味”があるのだと思う。
そこでしか得られなかった学びが必ずある。
💬 眞由子より
私は、痛みを通してしか気づけなかったことがたくさんあります。
でも今は、その痛みさえも私の人生の“副産物”だったと思える。
それが、私にとっての“癒しと悟り”の始まりでした。
副作用を“悪いこと”ではなく、“起こるべくして起きた反応”として受け止められるようになったとき、人生の痛みは“学び”に変わる。
🪞あわせて読みたい
👉 それは支配ではなく防衛だった/『毒親』と呼ばれた母親の孤独

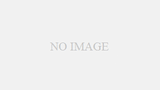
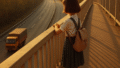
コメント