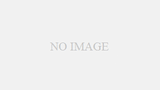まず最初にはっきりと区別しておきたいことがあります。
私は「毒親」という言葉の使われ方に強い違和感を持っていますが、ネグレクト(育児放棄)、身体的暴力、性的虐待などは、そもそも“毒親”という言葉で括るべきものではありません。
これらは、親子の関係性の問題ではなく、明確な人権侵害であり犯罪です。
それを“毒親”というラベルの中に一緒くたに押し込めてしまうことは、本来、真剣に語られるべき被害の深刻さまで曖昧にしてしまう危険があります。私はこの線を明確に引いておきます。
第1章/「Toxic Parens」
そもそも「毒親」という言葉は、スーザン・フォワードというアメリカの心理学者による著書
『Toxic Parents(邦題:毒になる親)』から来ています。
この本が日本で翻訳出版されたのは2001年のことです。
しかし、原書でも邦訳でも、「毒親(どくおや)」という言葉は使われていません。
あくまで「毒になる親」について語ったもので、
目的は“糾弾や断罪”ではなく、自分自身の心の回復でした。
第2章/日本で火がついたきっかけ:田房永子さんの『母がしんどい』
その後、2012年に田房永子さんによるコミックエッセイ『母がしんどい』が出版されます。
これは、母親との複雑な関係を描いた個人的な体験記であり、読者の共感を大きく呼びました。
「自分にも思い当たる節がある」「私の親もこれだ」
「親との関係にモヤモヤを感じていたのは、自分だけじゃなかった」
こうして、“毒になる親”という概念が、より身近な語り口で可視化されていったのです。
そしてこの頃から、日本で“毒親”という略語が使われ始めました。
第3章/マスメディアが作った共通認識
本は興味がある人しか手に取りません。
でも、テレビは違います。
テレビは、興味がなくても目や耳に入ってしまう情報です。
2019年頃から、新聞やNHKをはじめとした地上波の番組が、”毒親特集”を組むようになります。
• NHK『クローズアップ現代』
• NHK『あさイチ』(2022年)
• FNNプライムオンライン
• 朝日新聞による連載「さらば毒親」 (2024~
こうした大手メディアが一斉にこのテーマを取り上げたことで、
「毒親=社会問題」というイメージが定着していきました。
第4章/「当てはまらない人いるの?」
テレビやネット記事でよく紹介される「毒親あるある」や「毒親育ちの特徴」リスト
• 子どもの人格を否定する
• 感情的に怒鳴る
• 自分の価値観を押しつける
• 子どもをコントロールしようとする
•人の顔色ばかり気になる
まだまだ他に沢山あります。
でも、ちょっと待ってほしいのです。
これを読んで、「一つも当てはまらなかった」と言える人はどれくらい、いるんでしょうか?
人間には、「自分が危険に晒されていないか」を無意識に確認する防衛本能があります。
だからこそ、こうしたリストを見ると、
“自分にも当てはまるかも…”と、忘れていたような些細な記憶をわざわざ探しに行って掘り起こしてしまうのです。
でもそれは記憶の切り取りでしかない為、本当は親が子供を護るための防衛だったのかもしれない不器用な接し方さえも、「毒」として認識してしまうかもしれません。
”言葉が記憶を塗り替える”瞬間ですね。
おわりに/この言葉は、私たちを癒したのか?
「毒親」という言葉が、心の整理のきっかけになった人もいるでしょう。
でも、ただの“ラベル”として使われるようになったとき、
その言葉は自分と向き合い、自分の人生を生きるという 本質からは、かなりズレたものになってしまいます。
そもそも、誰が?何故この言葉が広まったのか?
どんな意図で?
そして、広まったことで私たちの何が変わってしまったのか?
私は、もう少しそのことについて考えてみたいのです。
つづく…。
【参考リンク】
♣️NHK『あさイチ』毒親特集(2022年)
https://www.nhk.or.jp/asaichi/archive/ 220328/1.html
♣️朝日新聞「さらば毒親」(連載)2024
https://www.asahi.com/sp/rensai/list.html?id=2151
♣︎2019年2月7日「一番の敵は『毒親』でした 虐待サバイバーたちの叫び」はリンク🔗が見つけられませんでした。
♣️FNNプライムオンライン “毒親”
https://www.fnn.jp/subcategory/dokuoya