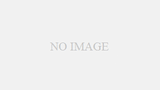ここで述べるのはあくまで仮説です。「毒になる親」と訳した翻訳者の判断を批判するものではなく、言葉のニュアンスが社会に与えた影響について考えてみる試みです。
言葉の選び方が社会を変える
「毒親」という言葉は、今や誰もが知るほど世間に浸透しています。親との関係に悩む人の間では、一種の共通語になっていますが、そもそもこの言葉はどこから生まれたのでしょうか。
原書のタイトル Toxic Parents (1989年スーザン・フォワード )は直訳すれば「有害な親」ですが、
本語版では「毒になる親」と訳され2001年に発売されました。そして、この本のタイトルだけで、中身を深く理解していない人たちが、親子関係を語る社会的空気を大きく変えたと私は感じています。
「毒」と「害」がもたらすイメージの違い
もし仮に「害になる親」と訳されていたら、状況は少し違ったかもしれません。
「毒」という言葉には強烈な危険性や拒絶のイメージがあります。
言い換えれば、親の存在自体が致命的に危険であるかのような印象を与え、手に取った瞬間から感情的な反応を誘発します。
一方で「害」という言葉は、抽象的で冷静です。
「害になる親」と聞いても、多くの人は「距離の取り方を考える」「自分に悪影響を及ぼす部分を見極める」といった論理的な考え方に向かいやすいでしょう。
本のタイトルは、まず手に取ってもらうための「フック」であり、内容の理解以前に注目させる役割があります。「毒」という言葉は一瞬で危険や衝撃のイメージを喚起し、SNSや口コミで広まりやすい。一方、「害」ではマイルドすぎて注目を集めにくく、話題になりにくいのです。
つまり、言葉ひとつで本の売れ行きも、社会的インパクトも大きく変わります。
ただ、ここで一つ言っておかなければならないことは、翻訳版において毒親という言葉は一切使われていません。
あくまでもタイトル通り、「毒になる親」なのです。
自己啓発市場との関係(予告)
これが毒親として広まった背景には、一兆円とも言われる自己啓発市場も無関係ではないと推察しますが、これについてはまた後日。
「毒親」という言葉が残した課題
毒親という言葉が強すぎるあまり、親を「糾弾すべき対象」として扱う風潮を生んでしまい、「毒親」というラベルが独り歩きし、冷静な分析や対話よりも、断罪やレッテル貼りに偏る傾向が大変多く見られます。
もし「害になる親」というマイルドな表現だったら、もっと建設的な議論が広がった可能性もあります。
言葉はただの表現ではありません。
それは、人の感情や社会の空気を左右する力を持っています。
特に我が国日本では、古くから言葉には魂が宿ると伝えられて来ました。
日本文化の根底には言霊の思想があると思っています。
日本社会に広まった、概念も定まらない言葉が社会現象を生み出し、親子や家族の絆や在り方に影響を与えた…。
そんな例のひとつが毒親という言葉ではないかと私は思っています。