「ブログに込める想い」でも書いたのですが、私は“言葉の力”を信じています。自分から出た言葉は、自分にも放った相手にも影響を与えます。
このブログタイトル「毒親と呼ばないで」には、親に見捨てられた私自身の体験から得た学びや願いが、強く込められています。
世の中に優しさが足りない気がする
最近の世の中は、誰かの欠点を見つけて、責めることが当たり前のようになっていると感じます。
失敗した人には「自己責任」
思い通りに愛情をあたえてくれなかったら「毒親」
確かに、失敗は自分の責任かもしれませんし、親に理解されず苦しんだ人も多いでしょう。
けれど、簡単に言葉で片づけてしまうのは、あまりに背景を無視しすぎてはいませんか?
親も生身の人間、神ではありません。
余裕のないときもあれば、愛し方を誰からも教わらずに手探りで生きてきた人もいる。
そんな存在を、たった一言で「毒」と呼んでしまうのは、あまりに冷たい、心無い言葉だと思います。
最低限の責任を果たしてくれた親を、“毒”と呼ぶことへの違和感
犯罪や虐待は、もちろん別次元の話です。
けれど、食べさせて着せて、学校に行かせ、病気のときに看病してくれた…
それだけでも、立派に“親の責任”を果たしてくれています。親は子育てだけではなく、沢山のものを抱えて生きています。
疲れて感情的に暴言を吐いてしまったり、態度に出てしまうこともあります。
子どもにとっては、確かに意味不明で心の傷になり得る出来事かもしれません。
私もそうでした。幼い時、母のご機嫌ばかり伺っていました。
他所のお母さんが羨ましいと、何度思ったことかしれません。
一緒にいることが恥ずかしいと思ったこともあります。
でも、その人が自分を生んで、育ててくれた親だという、変えようがない事実に、「毒親」というラベリングをすることは出来ませんでした。
世の中には優しさを搾取する人がいるのも知っている
もちろん、世の中には、人の優しさを利用する人がいることも知っています。
家族でも、他人でも、“思いやり”を都合よく使う人は確かにいます。
でもだからといって、「誰も信じない」「全部自己責任」と言い切ってしまう社会は、あまりに救いがないと思うんです。
「親を毒親だと切り捨て、他人の失敗を自己責任と言い放つ」
そんな世界で、人はどうやって立ち上がればいいのでしょうか。
これでは、誰も安心して失敗できない。
誰も、誰かの弱さを受け止められない。
当たり前ですが、子どもは親の分身ではありません。
いつかは自分の足で歩き出し、自分の人生を選んでいく存在です。
それでも、子どもが小さいうちは、この大変さが一生続くような気がして、絶望しそうになることもあります。
親も、永遠に親でいられるわけじゃない
でも、ちゃんと終わりは来る。
子どもは親の手を離れ、親もまた、自分の人生に戻っていく。
子どもを“自立できる人間”に育てることこそ、
親の大切な役割。
だから親はどこかで「手放す覚悟」を持たなければならない日が来る、
それは想像よりもキツい現実です。
愛しているからこそ、手放すのは苦しい。
でも、その痛みを通して、
「この子はもう自分の力で生きていける」と信じる強さが生まれる。
その覚悟と向き合ってら生きてきた人たちまで
“毒”と呼ばれてしまうのは、あまりにも悲しいことです。
世知辛い時代だからこそ、せめて親子は思いやりを忘れずに
今の世の中では、失敗を恐れて行動できなくなったり、責められるのを恐れて息苦しくなったりする人が増えています。
世知辛い世の中だけど、せめて、親子だけは思いやりを忘れずにいたい。
完璧じゃなくてもいい。
上手に愛せなくてもいい。
言葉の奥にある“想い”まで感じ合える関係であれたら、それだけで、もう十分なんじゃないかなと思います。
💠「毒親と呼ばないで」に込めた願い
私は、「毒親」という言葉が嫌いです。
それは、親を擁護したいからではなく、人たいして、切り捨てる言葉を使いたくないから。
タイトルを、「呼ばないで…」にしたのは
その一言には、「人間を簡単に見限らないで」という願いが込められています。
親も、子も、誰もが不器用で、誰もが誰かを傷つけ、そして愛してきた。
その不完全さの中にこそ、本当の優しさや、理解の芽があるのではないでしょうか。
終わりに
私は、世の中がもう少しだけ、“人に優しくあれる場所” であってほしいと思っています。
責めるよりも、理解するほうへ。
決めつけるよりも、問い直すほうへ。
「毒親と呼ばないで」という言葉は、そんな想いを込めた、私なりの小さな祈りです。

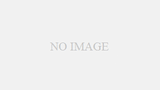
コメント